工場立地法の「既存工場」には、どんな工場が該当するの?
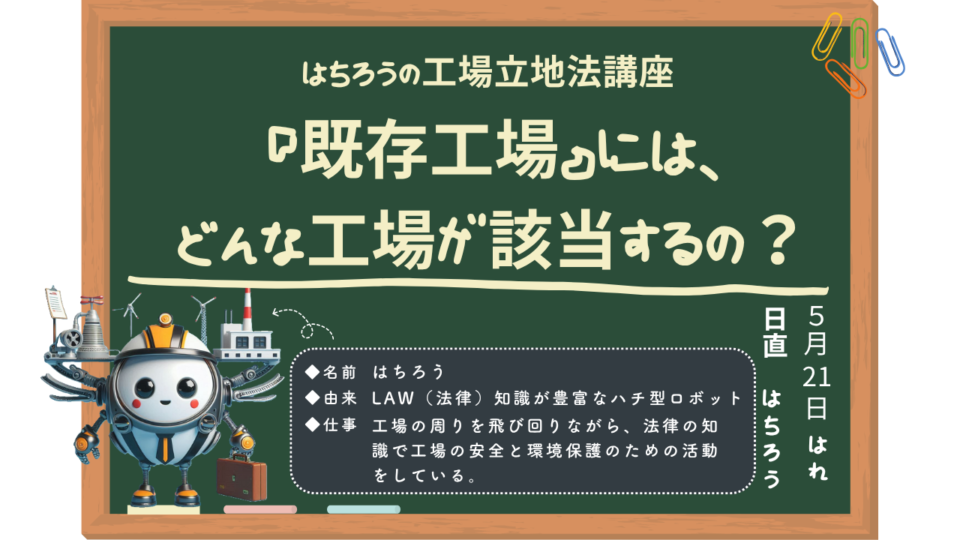
こんにちは!
今回は、工場立地法に出てくる「既存工場」について解説します。
「既存工場」の定義を理解しておかないと、届出や計画時に思わぬトラブルにつながることもあるから注意しましょう!
◆ そもそも「既存工場」って何?
工場立地法が施行されたのは昭和48年(1973年)。
この法律は主に、新たに工場を建てる際の緑地や環境施設の確保などのルールを定めたものです。
しかし、当然ながら法律施行時点で既に稼働していた工場も全国に数多く存在していました。
この時に存在している工場まで、法律の新しい基準を一律で求めるのは現実的ではありません。
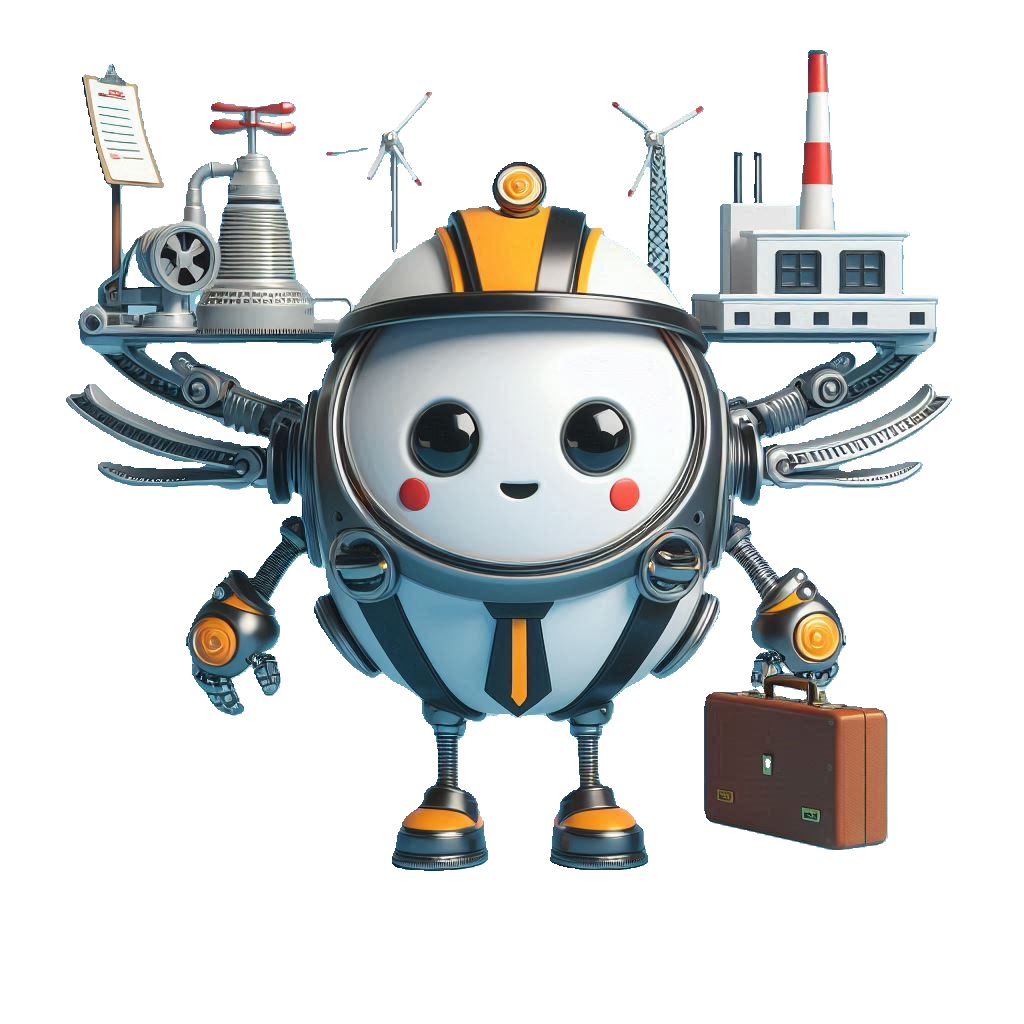
はちろう
いきなり“工場敷地の一部を緑地にしなさい”なんて言われても、対応できないよね?
そうだよ。昔からある工場に突然新しいルールを押し付けられても困っちゃうよ…

工場管理者たろう
そのため、本法律では既に建っている工場、つまり「既存工場」には新設工場とは別の取り扱いを設けることになりました。
「既存工場」とは、昭和49年6月28日以前に建設済み、または昭和49年6月28日時点で建設工事中の工場を指します。
既存工場には緩やかな規制が適用されることとなり、段階的な対応(たとえば緑地を徐々に増やすなど)が認められており、 この“段階的な対応”は、以下のとおり「工場立地に関する準則の備考」に定められています。
| 「工場立地に関する準則の備考1」より抜粋 |
| 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、昭和49年6月29日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第1条の規定に適合する生産施設の面積、第2条の規定に適合する緑地の面積及び第3条の規定に適合する環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。 |
自分の工場が「既存工場」かどうかは、この日付を基準に判断できるし、既存工場に該当する場合は段階的に対応すれば良いんだね!

工場管理者たろう
◆ 増設・建て替え時には要注意!
たとえ「既存工場」に該当する工場であっても、昭和49年6月29日以降に既存工場の生産施設を増設したり、建て替え(スクラップアンドビルド)を行う場合には注意が必要です。
その変更内容によっては、工場立地法で決められている既存工場の計算式で算出した面積の生産施設や緑地整備が求められますし、変更の届出も必要になります。
なるほど、既存工場でも何かを変更しようとする時にはちゃんと対応しなきゃいけないんだ!知らなかった!

工場管理者たろう
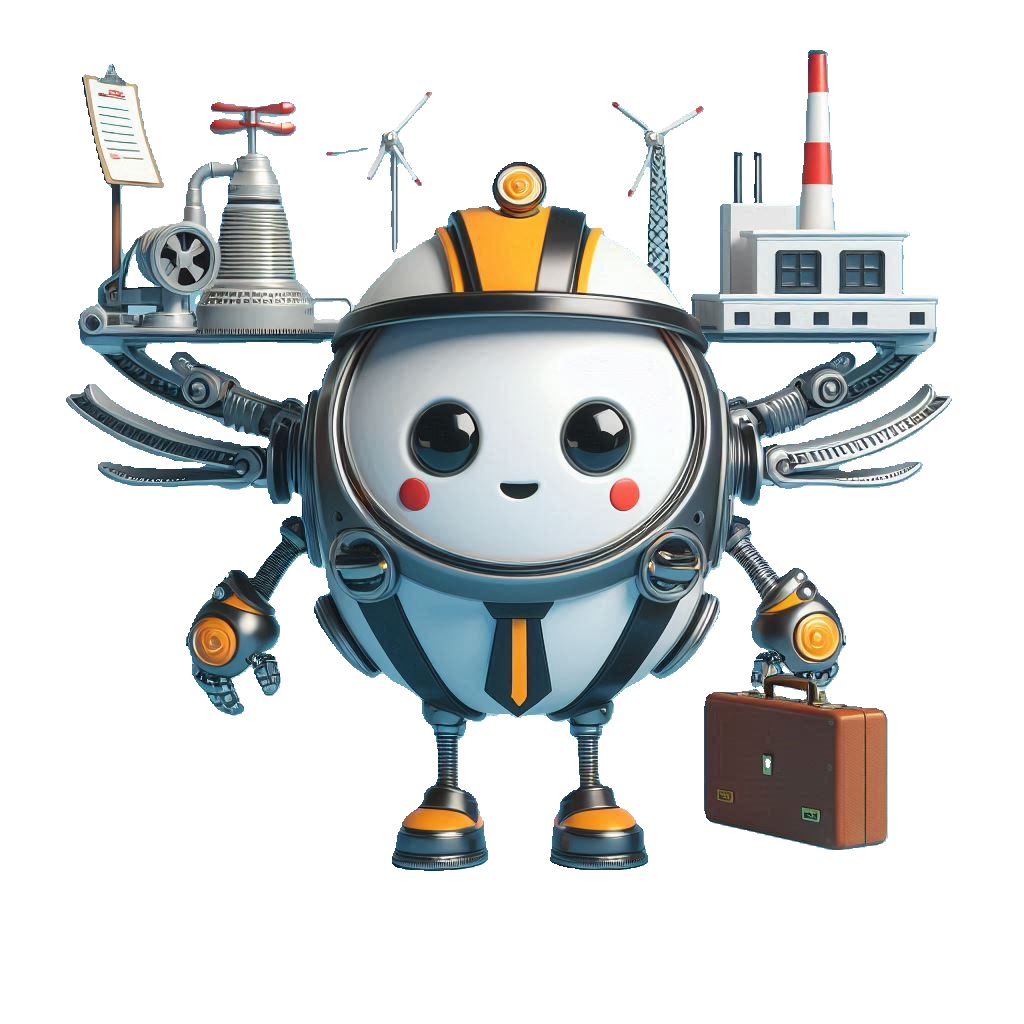
はちろう
そうそう。“既存工場だから大丈夫”と思ってると、思わぬ指摘を受けることもあるから注意してね
◆ 実務ではどう対応すべき?
既存工場かどうかの判定、そして増設や変更時の数値計算については実務の中で非常に重要なポイントになります。ここで役立つのが、以下の参考資料です。
・電子書籍『実務者のための工場立地法』の「第5章 調査・測量と数値の算出」
・紙の書籍『工場立地法セミナーテキスト』の「第6章 既存工場における準則計算書の作成」
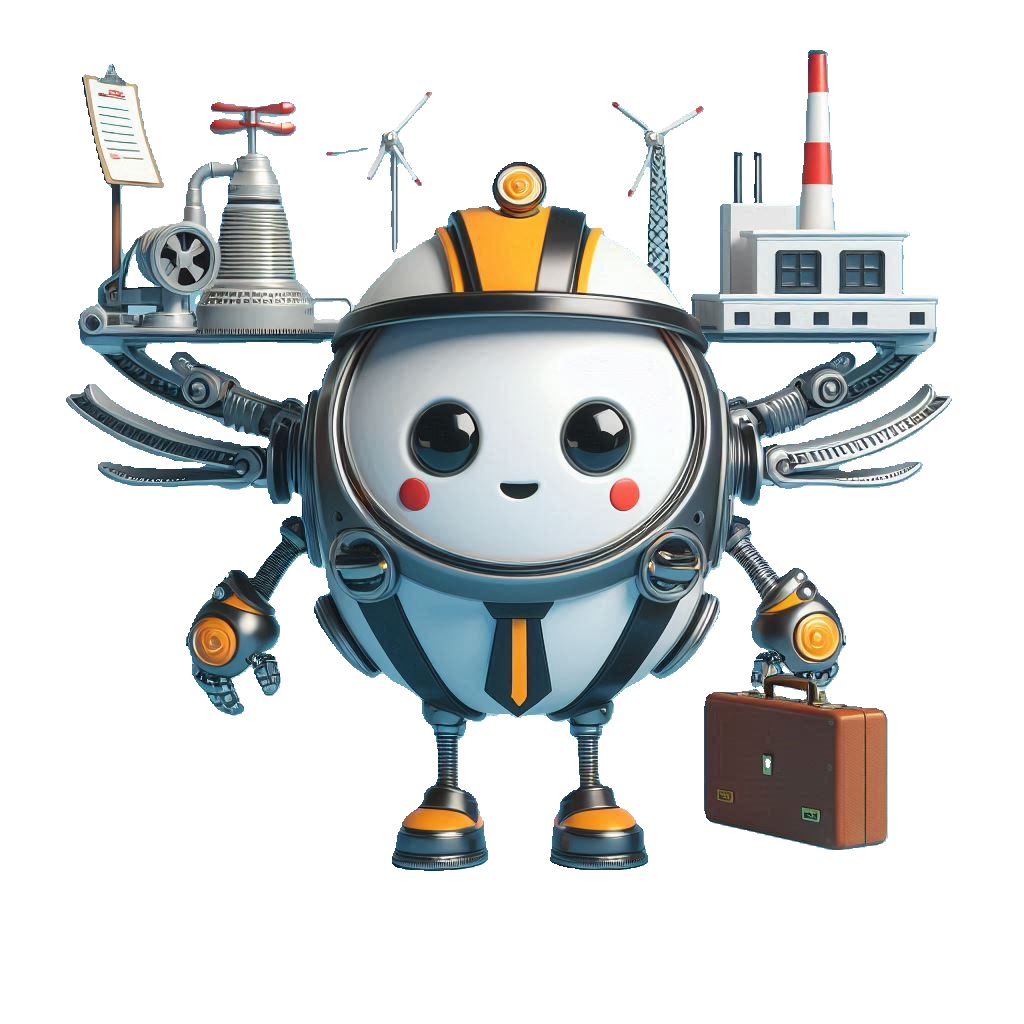
はちろう
実務で迷ったときにすぐ確認できるから、机の引き出しに1冊入れておくのがおすすめだよ
◆ まとめ:既存工場の定義を正しく理解しよう!
“うちの工場は既存工場だから関係ない”と思っていたら、実は増設の際にルールが適用される対象だった!!というケースは少なくありません。
✅既存工場の基準日は昭和49年6月28日であること
✅増設や建て替えの際は特例に基づいた面積計算が必要なこと
この2点を押さえておくことが、トラブル防止とスムーズな届出対応の第一歩になります。
僕はセミナーテキストを持っているから第6章をしっかり読み返しておくね!

工場管理者たろう
📌 次回予告
次回は、「変更等の届出から90日間は工事着手できない?30日まで期間短縮する方法」について解説します。このBLOGで紹介した「届出違反ケース②」を補足する回だよ。
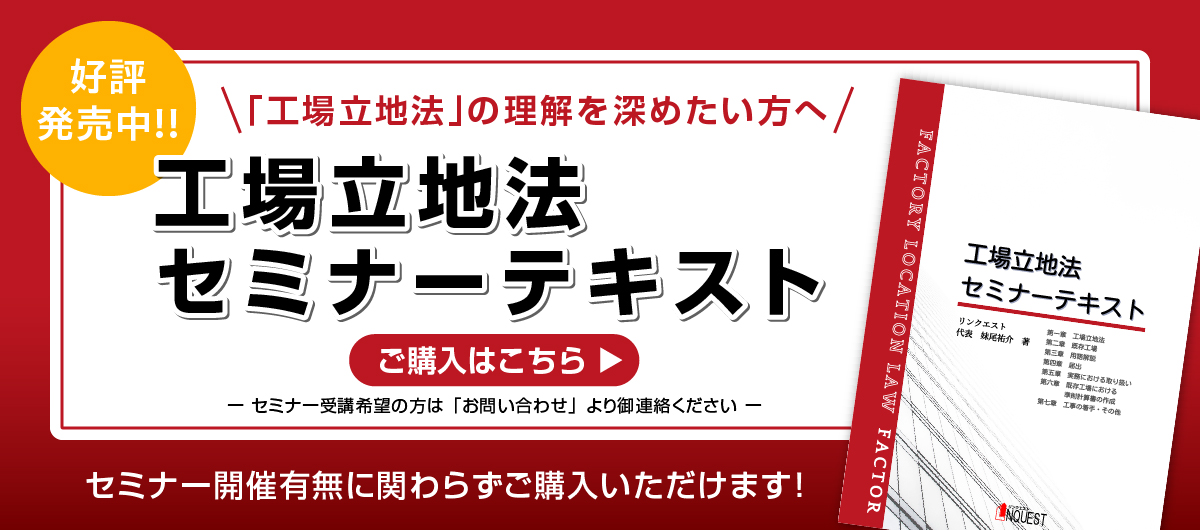 |
 |


